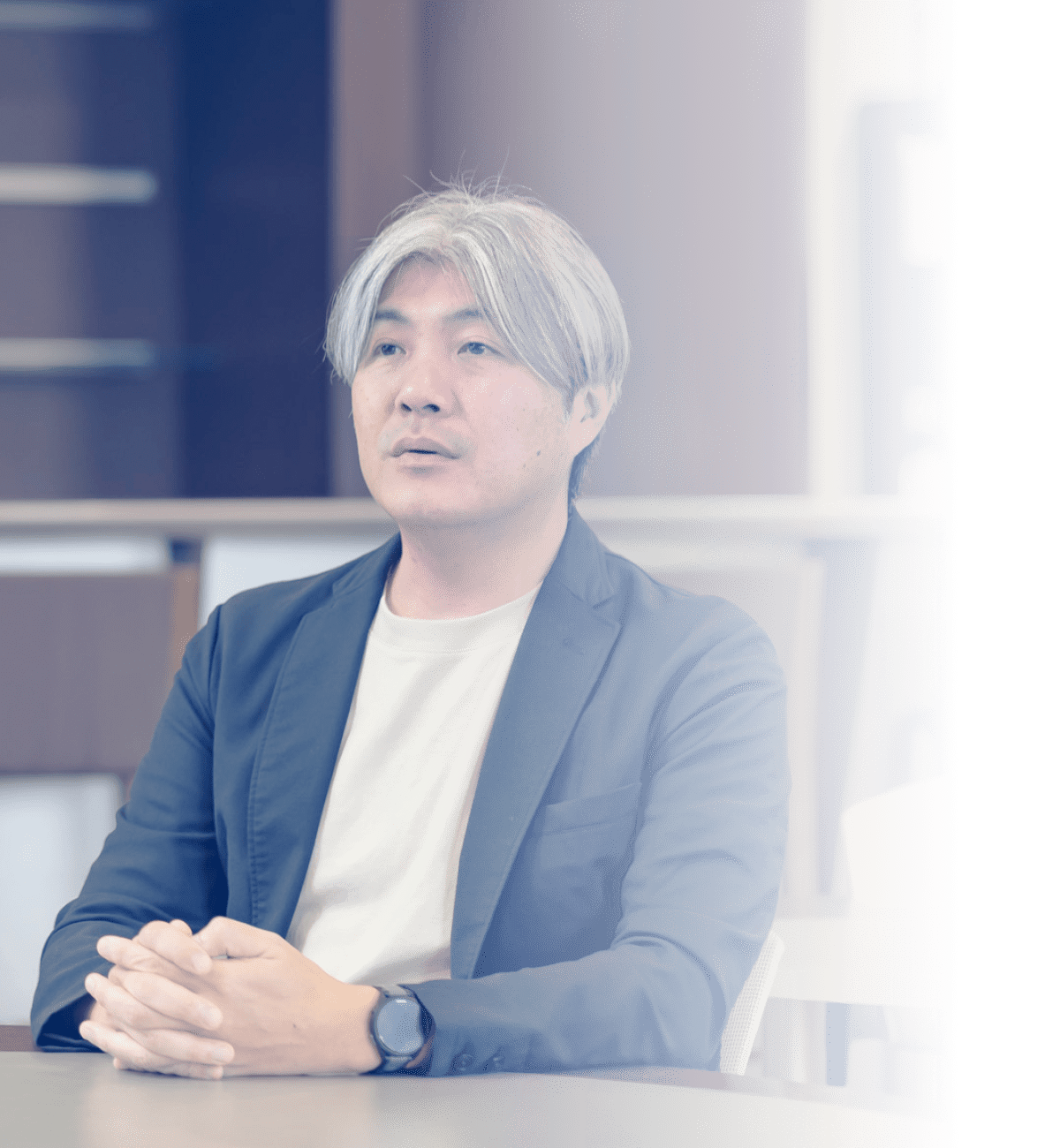
株式会社インテージテクノスフィア
インサイトプラットフォーム本部 本部長
渡辺 聡
Satoshi Watanabe
1999年社会調査研究所(現:インテージテクノスフィア)に新卒入社、顧客向けのシステム開発を担当。2000年に企画部、2008年にリサーチテクノロジー本部に異動、内販のシステム開発を担当。2014年インテージテクノスフィア設立に伴い転籍。2023年より本部長。
Interviewインタビュー
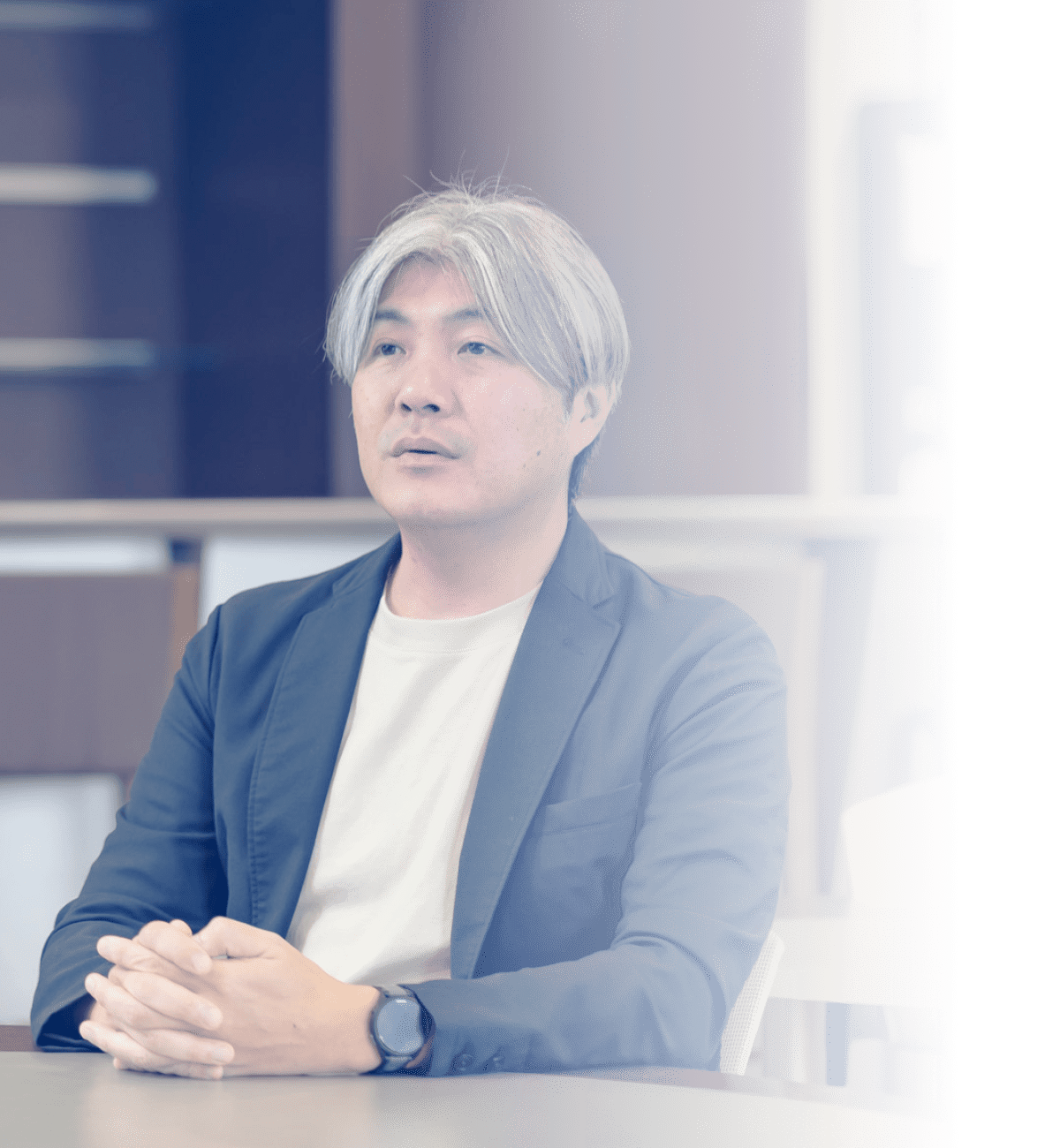
株式会社インテージテクノスフィア
インサイトプラットフォーム本部 本部長
渡辺 聡
Satoshi Watanabe
1999年社会調査研究所(現:インテージテクノスフィア)に新卒入社、顧客向けのシステム開発を担当。2000年に企画部、2008年にリサーチテクノロジー本部に異動、内販のシステム開発を担当。2014年インテージテクノスフィア設立に伴い転籍。2023年より本部長。
現在の業務内容について
1999年に当社の前身である社会調査研究所に入社しました。最初に配属されたのは顧客のシステム開発を行う部署で、そこでは1〜2年ごとにさまざまな案件に携わりました。案件規模は大小さまざまでしたが、大企業からの仕事を受託することもありました。だいたい2〜3人のチームで行う案件が中心で、社内ワークフローの構築やWEBサイトのログ集計、官報のPDFファイルのデータ化などを行うシステムの開発をしていました。
その後に異動した企画部では、調査事業で培ったノウハウをシステムに展開する業務を担当しました。具体的には、宿泊施設の宿泊者データをもとに、リピート可能性が高い方へ効率良くDMを送付するといったマーケティング支援ツールの開発に携わりました。その他では、金融業界向けにデータを活用した営業支援システムを手がけたり、全国に営業担当が3,000人いる顧客向けに商品の陳列状況や自動販売機の有無などを現地で調査・報告しやすい携帯用業務アプリの開発を行ったりしました。
その後、2008年にインテージリサーチ事業のシステム開発を行う部署へ異動し、2014年にインテージテクノスフィアへ転籍、リサーチテクノロジー本部に配属されました。
このリサーチテクノロジー本部では、インテージグループのマーケティング支援事業の中でも中心となるパネル事業のシステムを担当しています。このシステムには「パネルデータを集める」「作る」「顧客へ届ける」というデータの流れがあり、データの運用や集計、商品マスターのメンテナンスなどを行っています。
このパネル事業はインテージグループの中でも最大規模の収益を生み出す事業です。だからこそシステムを安定稼働させることと、時代に合わせてシステムをリニューアルし、事業成長を支えることが使命です。そこで私は2023年から本部長として、インテージのパネル事業の責任者たちとともに今後の方向性を検討したり、開発計画の策定や進行管理、トラブル対応を行ったりしています。
社内でのAWS活用の第一人者として。AWS導入の先陣をきる案件に着手
印象に残っている仕事のひとつとして、2015年に始動した「小売業界との関係性改善プロジェクト」があります。従来の全国小売店パネル調査「SRI®」では、当社が小売業界からPOSデータを購入し、それを基に分析を行っていました。そのため、小売店との契約が終了すると、その店舗のデータが取得できなくなるという課題がありました。そこで、当社が小売業界へなんらかの価値を提供できれば、当社が小売業界にとってより欠かせないパートナーとなれるのではないかと考え、このプロジェクトが立ち上がりました。これは、既存のシステムをリプレイスするのではなく、新規でシステムを構築しようというものだったため、リスクも少ないと判断し、当時は社内でも珍しかったAWSの導入を決めました。
もちろん当初は、担当したチームにもAWS導入の知見が乏しかったため、社員も協力会社の方々も一緒にAWSの研修に参加して基礎知識を学んだり、AWSの担当者にヒアリングを重ねたりしながら、少しずつ理解を深めて進めました。幸いにもチームには若いメンバーが多く、「オンプレミスの方がよかった」といったネガティブな声も出ず、柔軟に取り組めたのは良かったですね。結果的に、このプロジェクトが成功したことで、パネル事業において初めてクラウドサービスを活用した実績と信頼が生まれ、社内の認知も高まりました。
そしてこの経験が後押しとなり、インテージグループ最大のプロダクトであるパネル調査の刷新プロジェクトへとつながりました。これは従来の全国小売店パネル調査「SRI®」を見直し、クラウドサービスを活用した新しい全国小売店パネル調査「SRI+®」を立ち上げるというものでした。以前の「SRI®」では、全国に20万店ある小売店舗の中から選定したサンプル店舗のデータをもとに、全国の販売動向を推定するという手法が用いられていました。一方、新システム「SRI+®」では、従来のサンプリング手法と全店舗分のいわゆるセンサス(全数)データを織り交ぜて集計・分析できる仕組みへ進化し、これにより、より高精度な小売店パネルを導き出せるようになりました。顧客にとってより信頼性が高く、かつ高付加価値なデータを提供できるようになったのです。
スピード優先で技術導入する企業文化
当社では、このように新しい技術を導入する際、「できそうならまずはやってみよう」というスタンスで、スピードを優先することが多いです。その上で運用しながら課題があれば修正し、最適化していきます。特にパネル事業は、インテージグループの中でも最大の収益源ということもあり、ある程度経費に余裕があることもあって、多少コストがかかってもスピードを優先しています。
2024年4月に実施した全国消費者パネル調査「SCI®」のリプレイスを行ったときも、同様でした。
従来の「SCI®」は、全国の消費者約5万人に独自のバーコードスキャナーを配布し、購入商品のバーコードをスキャンしてもらった上で、購入金額のデータとともにパソコンで送信してもらい、対価として報酬を払う仕組みで、毎年何億円もの維持コストが発生していました。
一方、新システムは消費者が自分のスマートフォンでレシートを撮影・送信するだけで運用できるようになったため、消費者の手間が減った分、報酬も抑えることができ、運用コストが大幅に削減できる見込みがありました。
もちろんシステムのリプレイス方法については、万全の状態に仕上げてから行うという考え方もあるかと思いますが、当社の場合、旧システムの維持コストが嵩むよりも、早く新システムへ切り替える方が最終的なコストメリットが大きいと判断し、新システムは「ひとまず動けば問題ない」という考え方のもと、リリースに踏み切りました。そしてリリース後に出てきた課題に対して、現在も改修を重ねながら最適化を目指しています。
今後の抱負とこれから入社する方へメッセージ
私たちの部署の基本は、「安定的に」「データを集める」「加工する」「届ける」ことです。そうした一見地味に思える作業も、日本の生活者の姿を正しく顧客に届け、よりよい世界を作っていくことにつながっています。そうした意味では、日本のマーケティング活動を根底から支える「誇り」を持てる仕事だと思います。
また私たちは、インテージグループのマーケティング支援事業をシステム面で支えているため、事業が成長し拡大すれば、私たちの役割も自ずと拡大し、成長します。業界全体を見ると経営統合などを通して規模を拡大する会社もありますが、そうした企業に負けず成長し続けるためには、既存サービスにも、生成AIなどの新しい技術を常に取り入れ、より良いサービスとなるよう進化していく必要があります。
日本中からデータが集まる当社で、多種多様なデータに日々触れながら、新しい技術を試し、新しい価値を生み出していく。そんな仕事をしたいという人に、ぜひ仲間になっていただきたいですね。
この記事は取材当時(2025年7月1日)の内容です。