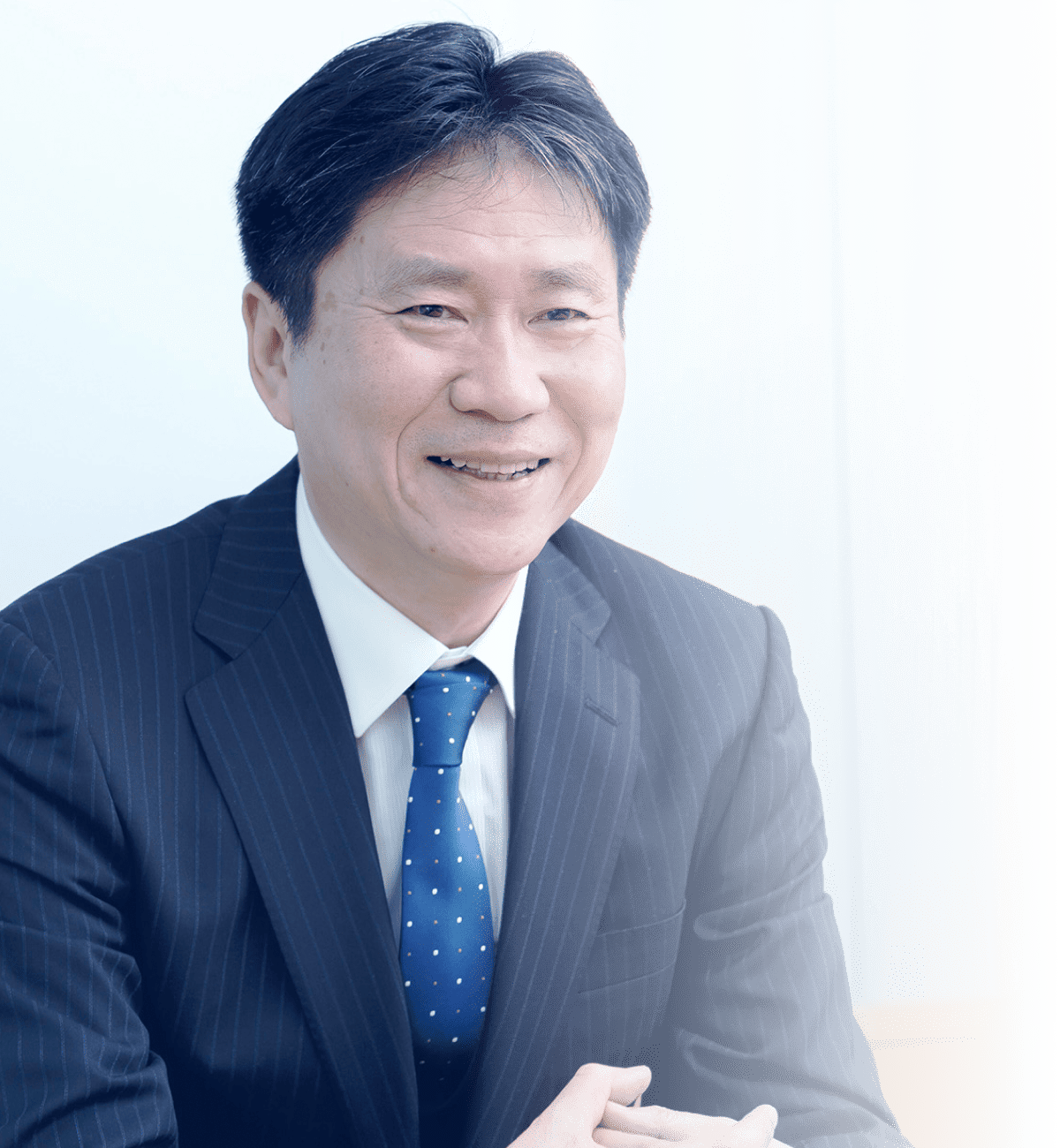
執行役員(取締役/CTO)
秦 一雄
Kazuo Shin
1998年インテージにエンジニアとして入社し、リサーチ部配属。 2012年システム部へ部長として異動。 2014年インテージテクノスフィア設立に伴い転籍。 2016年執行役員(取締役/CTO)就任。 より精度の高いデータ提供の実現のためにインテージ テクノスフィアの取締役としてSnowflake導入のプロジェクトをリードしてきた点を評価され、 2021年「Data Drivers Awards」の「DATA EXECUTIVE OF THE YEAR」受賞。
Interviewインタビュー
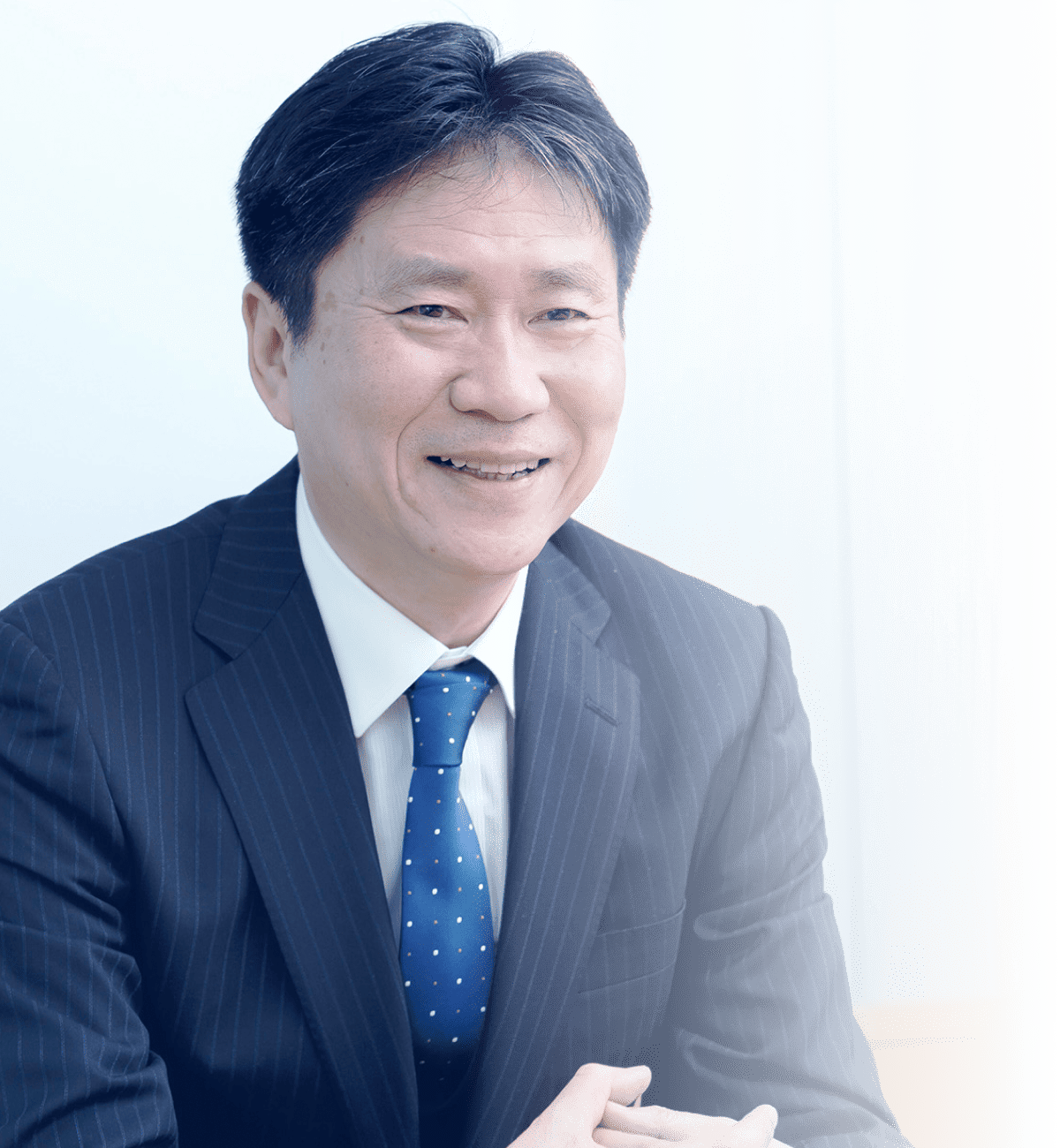
執行役員(取締役/CTO)
秦 一雄
Kazuo Shin
1998年インテージにエンジニアとして入社し、リサーチ部配属。 2012年システム部へ部長として異動。 2014年インテージテクノスフィア設立に伴い転籍。 2016年執行役員(取締役/CTO)就任。 より精度の高いデータ提供の実現のためにインテージ テクノスフィアの取締役としてSnowflake導入のプロジェクトをリードしてきた点を評価され、 2021年「Data Drivers Awards」の「DATA EXECUTIVE OF THE YEAR」受賞。
中途入社から CTO になるまで
私は1998年に当社の前身であるインテージにエンジニア職として中途入社いたしました。その後、マーケティングリサーチの部署に配属され、新規事業の商品開発などを行いました。2012年にはシステム部の部長として異動し、2014年に当社が発足。そして2016年に執行役員に就任いたしました。
私が入社した当時IT業界は急成長していて、今後の期待が高まっている業界であると感じましたし、中でもインテージはマーケティングリサーチの会社として頭角を現している時期でした。会社規模としても約1,000人の社員が在籍しており、大規模な案件からチャレンジングな案件まで、多種多様な仕事ができる環境がありました。また当時の社長は先見の明を持っており、今後はIT人材がさらに求められていくと考え、社員の教育を大切に思っている方で、面接の際に社長自らが新しいことをやりたい、社員に裁量権を持たせたいと言ってくれたことが、入社の決め手の一つでした。
実際に入社してからは、新規のプロジェクトにチャレンジして赤字を出すなど失敗したこともありましたが、上司が私を守ってくれて、次のプロジェクトも任せてもらいました。当社には、部下の挑戦や失敗に対して上司が責任を持つ文化があり、その社風のおかげで私自身はもちろんですが、多くの社員が成長していると感じています。
社員自らが新しい技術に挑戦する社風
私が入社した時も、新しいツールを導入してチャレンジしたいと言えば、たとえ費用が発生しても、上司はほとんど承認してくれましたし、新しい技術を試そうという社風は、インテージの時代から今まで引き継がれていると思います。技術の世界は常に進化しているため、現在も社員は常に新しい技術にアンテナを張っています。過去には2019年にSnowflakeを、2021年にクラウドサービスを他社に先んじて導入するなど、新しい技術を使った提案・開発を行い、その後、それら技術を中心とした案件を事業化しています。
顧客はリスクを恐れて新しい技術を用いることを避けることも多いのですが、まずはインテージグループ向けの内販業務で新しい技術を用いて、そうした技術基盤や使用事例を作ることにしています。インテージの業務で用いるデータは大量かつ複雑ですので、そこで培った技術やノウハウを、外販の顧客に対して展開することで、顧客の安心感を醸成することが狙いです。このようにグループとしての強みや総合力を活かし、ただ学ぶだけではなく、技術を顧客の本質的な課題解決に繋げ、新しい技術を事業に還元することを意識しています。
社内にはCTOオフィスという、各部署のメンバーを集めたCTO配下の組織があり、新しい技術を試したい人が予算を使える機会があります。
例えば、2023年には、当時入社2年目の社員が私との立ち話の中で、ChatGPTを活用した生成AIの新しい勉強会を提案してくれました。そこでChatGPTの有償版を導入するとともに、まだ若手で周囲を巻き込む力が十分でなかった彼に代わり、私が各部署から若手社員を集め、業務時間内に勉強会を開催しました。今ではChatGPTを用いてどのように自動コーディングすれば良いかなども勉強しています。
その他にも、技術に関する外部の勉強会に参加したければ会社が費用負担しますし、技術だけではなく、どのようにビジネスとして活用するかといった視座を高める勉強会も、社員自らがパートナー企業やITベンダーなどから探してきて、参加しています。新しい技術の取入れに積極的なところは当社の魅力の一つだと思います。
今後目指すエンジニア組織の生存戦略
社会的にDXへの関心が高まる今、SIerにとってとてもいい時期です。一方で、IT人材は2030年になる頃には40〜80万人足りなくなると言われています。しかし単にシステム開発するだけの従来型のIT人材は、むしろ今後余っていくでしょう。今後不足するのは、クラウドエンジニアやAIエンジニア、データエンジニアといった先端ITを扱ったり、顧客がITに精通していなくても顧客のニーズを理解し、最適な提案や開発を行い、時代に合わせてスキルを向上させたりできるような高度IT人材だと思います。そこで当社は高度な技術者を増やしていくことで、他社との差別化を図ろうと考えています。
すでに当社では下流工程の案件を受けるのではなく、上流工程から入って案件を受ける体制に変わってきています。要件定義や仕様書を作成、新しい技術を用いた高付加価値のある業務が社員の役割の中心です。
もちろん中には従来型のシステムを維持する部署もありますが、新しい技術を扱う部署の社員と勉強会などでつながり、互いに刺激しあう環境があります。そのため、たとえ前職で従来型のシステム開発を行っていた人であっても意識が変わりますし、業務を通じてスキルを身に付けていくことで、高度IT人材としてのキャリアを歩むことができます。
ただし高度IT人材であっても、上流から下流まで担当できることが求められるので、新卒採用を想定した場合、最初の3〜4年は下流工程で経験を積んで、その後、上流へシフトしていきます。その際、下流工程を経験している段階から上流工程の打ち合わせに参加し、顧客のニーズを理解するようにするなど、どんなレベルの社員でもあっても上流工程の意識の醸成を図っています。そんなふうに人材育成をしているからか、5年目にはPLになることが多いですし、優秀な若手の中には3〜4年目でPLになることもあるんですよ。
これから入社する方へメッセージ
当社は、長くお取引している顧客が多く、当社の社員は顧客の中に入り込んで伴走するため、顧客の課題の本質を理解し、きちんと提案すれば、大きな案件につながるチャンスがたくさんあります。その分、常に課題を考える努力は必要ですが、やりたいことがあれば、会社もサポートする環境が整っていますし、実際に業務として経験して自己成長できる会社だと思います。
そのためには、まず自分の価値を理解することが大切です。今までのキャリアや経験を最大限に発揮し、目指すキャリアイメージをきちんと実現していくことが、その人にとって1番幸せだと思っているので、会社はそのためのサポートをします。面接では、今後取り組みたい課題認識や、その課題に対して真摯に向き合うことができる方かを見ています。例えば、エンジニア社員で上流工程に携わりたい方であれば、上流工程に進むためにどのような努力をしてきたか、また、指示されたことをこなすだけでなく、率先して顧客とコミュニケーションを取り、顧客のニーズの本質を理解し、提案できる人であるかといったヒューマンスキルを見ています。当社の場合は、顧客に提案する際、営業だけではなくエンジニアも同行します。顧客からも「このエンジニアがいるから当社に依頼したい」と言われることもあるので、ヒューマンスキルは大切な要素です。
過去に中途入社した方の中には、前職はIT業界でPMをしておりエンジニアではないのですが、PMとしての物事の見方から顧客の課題を見つけ、それに対して解決策の提案書を作ってくるなど、プロジェクトを牽引している人がいます。自由に動いてもらった結果、現在は優秀な開発メンバー8人のマネージャーとして、最先端の技術を取り込んでデータ活用を図る、当社としても新しい事業領域で活躍しています。
このように、社風に合うかはもちろん、個々の個性を大切にする会社だと思います。
中途採用の場合、理想のライフスタイルがあると思いますので、それに合わせて最適な職種配置をするようにしています。中途入社された方の中には子どもがまだ小さいために時短勤務で働いている方もいます。インテージは一般的なSIerよりも女性の割合が多いので「女性ならではの働き方を受け入れる環境が当たり前である」という考え方が根底にあります。そのため入社後に結婚、出産、産休をとって、落ち着いたらマネージャーや部長になる女性が多いですし、男性も半年以上育休を取得する人が多いです。仕事と育児を両立する社員をサポートするため、復帰時には上司と面談し、時短勤務にするか、仕事量を減らすかなど、勤務時間や仕事内容を詳細に調整しています。1時間単位で休暇を取得できる制度があるので、それを活用している社員もいますね。それから子育てが落ち着いたら、新しくチャレンジしてもらえる体制もありますので、キャリアの分断はほとんどありません。
大切な社員が、自分の暮らしを維持できるという安心感の中で、やりたい仕事をしてもらったり、目指すキャリアに邁進してもらったりすることで会社が活性化していくことが私や、会社の望みです。
※この記事は取材当時(2025年2月19日)の内容です。