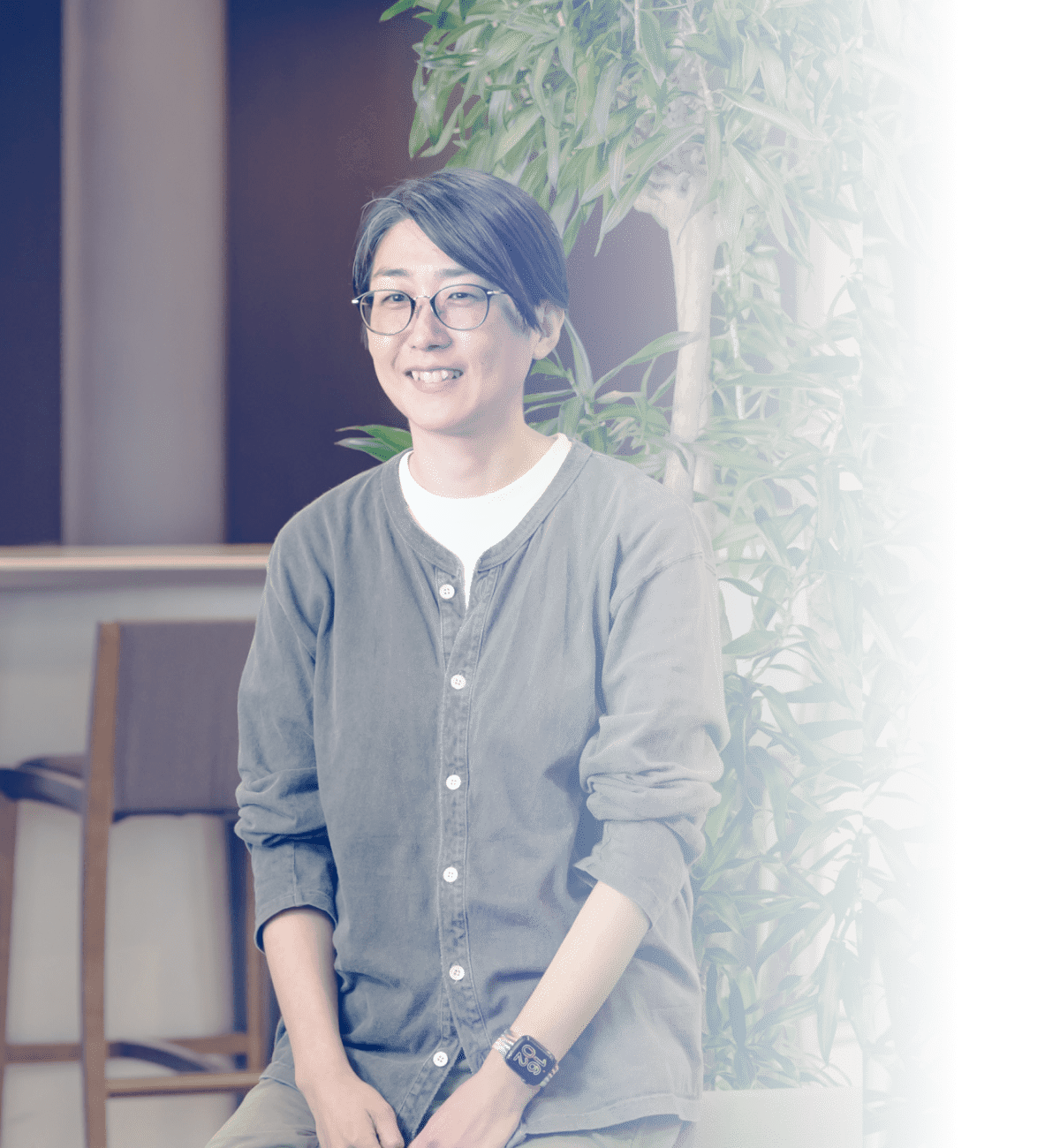
株式会社インテージテクノスフィア
インサイトプラットフォーム本部 リテールインサイトプラットフォーム部
第1グループ グループリーダー
城 裕子
Yuko Jo
2002年新卒入社、顧客向けのシステム開発を担当し、2006年にグループシステムの開発部署へ異動。2015年インテージテクノスフィア、リサーチテクノロジー本部へ転籍。開発1部に配属され、2019年よりグループリーダー。
Interviewインタビュー
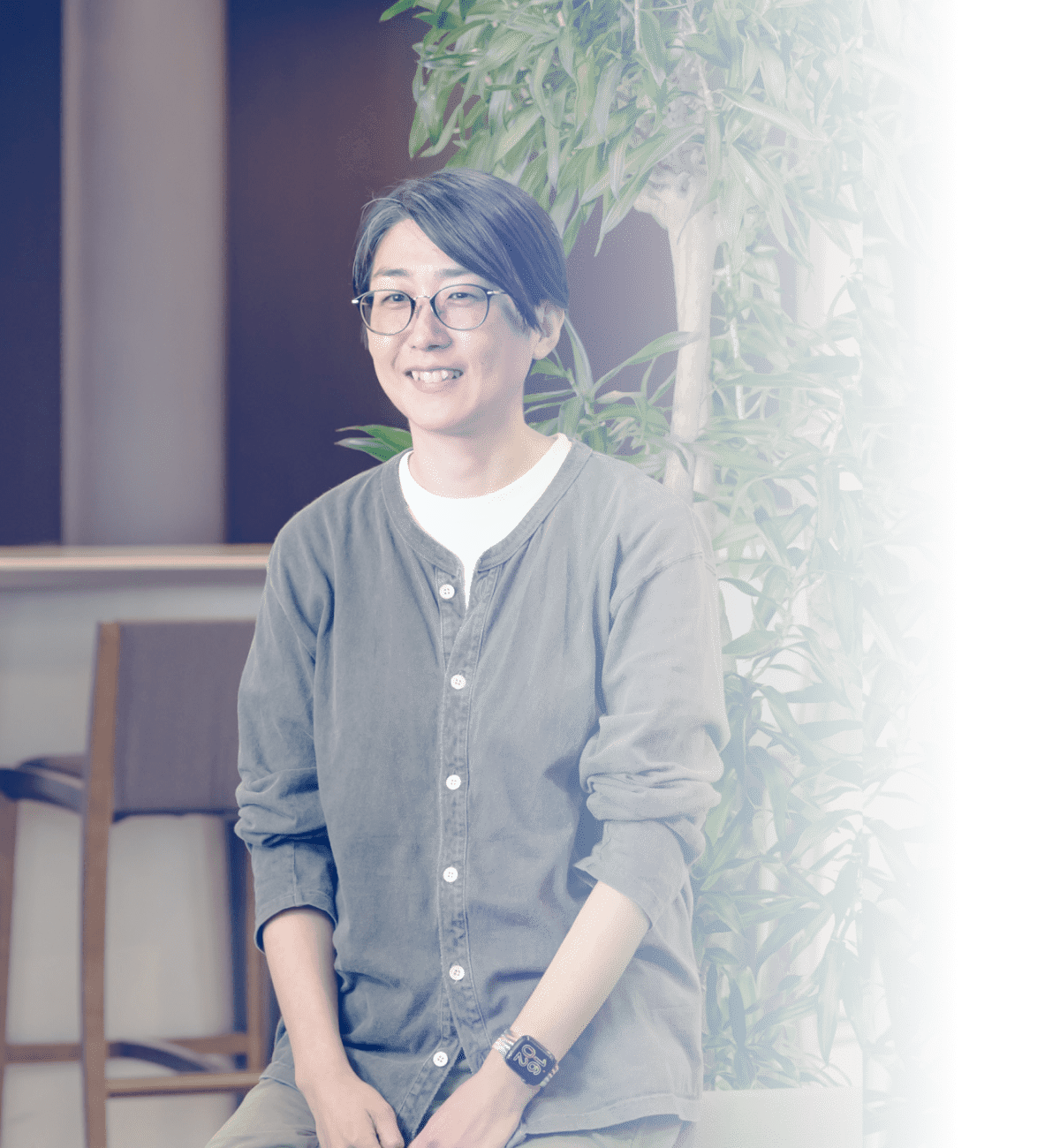
株式会社インテージテクノスフィア
インサイトプラットフォーム本部 リテールインサイトプラットフォーム部
第1グループ グループリーダー
城 裕子
Yuko Jo
2002年新卒入社、顧客向けのシステム開発を担当し、2006年にグループシステムの開発部署へ異動。2015年インテージテクノスフィア、リサーチテクノロジー本部へ転籍。開発1部に配属され、2019年よりグループリーダー。
現在の業務内容について
2002年に新卒で入社し、最初の5年は銀行系の不動産評価システムなど、顧客向けのシステム開発に携わっていました。その後約3年ごとに異動しながら、インテージのマーケティングリサーチビジネスを支えるデータ集計、パネルポータル、iCanvas®などの企画開発を担当しました。そして2015年にインテージテクノスフィアへ転籍し、マーケティングリサ―チ関連の部署でデータ集計システムの開発プロジェクトに参画しました。
私が担当しているのは、小売店から届くPOSデータに関わる「SRI+®」や小売店の店頭販促状況に関する「SPI」、EC関連の各データをクレンジング・加工しているほか、それらのデータのマスターを作成するシステムや加工済みデータを顧客へ送信するシステムなど、計6つのシステムです。それぞれのシステムにはリーダーがいるため、私はグループリーダーとして彼らと進捗確認を行い、必要に応じてサポートや調整をしています。
私たちが加工しているデータは、国内全体の売上を推計したデータとなっており、その商品の市場規模やシェア動向等、監査データとして顧客の経営判断の材料になりうる重要な情報です。そのためデータの加工作業は、毎日、毎週、毎月、決められたタイミングで確実に実施する必要がありますし、システムを安定稼働させることがミッションです。万一期限を守れなかった場合には、お客様の経営判断のミスや遅れに繋がるため、納期遵守は常に意識しています。
またデータの質を高めるための精度向上にも取り組んでいます。精度向上のための仕様についてはインテージ側が策定するため、私たちはそれをいかに早く正確に実現するかに注力しています。最近では、データの一部を変更した場合に、どのような影響が出るかをシミュレーションする取り組みも始めています。
自走するチームを育む「任せる」マネジメント
私はグループリーダーという立場ですが、自分自身が人材育成をしているという意識はあまりありません。強いていえば、何か良くない点があれば「それは違うよ」と伝えている程度です。
業務に関しては各システムのリーダーたちが非常に優秀なので、マイクロマネジメントしすぎず、ある程度任せることで自然と成長してくれていると感じています。例えば以前あるリーダーが別業務を担当することになり、2年目のメンバーにサブリーダーを任せたことがありました。すると役割が変わったことで本人の責任感が高まったのか、そのメンバーは私が細かく指示を出さなくても、自走できるようになりました。
そうした中で私が意識していることは、1on1で話を聞く時間を設けたり、Slackをこまめにチェックしたり、出社時に周りとの関係性を観察したりするなど、メンバーが困っていないか常に気にかけるようにしています。
また私たちの部署は、会社の主幹事業を支える大変重要な仕事である反面、データ加工など泥臭い作業が多い一面を持っています。メンバーにとっては成果が見えづらいといったネガティブなイメージがあると私は認識しています。メンバーがモチベーションを保てるように、インテージ側に働きかけて、私たちが加工したデータを顧客がどのように受け取り、どう評価しているのか、ポジティブな反応があればフィードバックしてもらえるようにしています。
「マミートラックには乗せない」社風がかなえる3人の育児との両立
3人の子どもの「母」になっても、自分らしくキャリアを築ける環境
私はこれまでに3回、育児休業を取得していますが、いわゆる「マミートラック」を感じたことは一度もありません。当社では「母」になっても自ら仕事の幅や量を制限しない限り、マミートラックに乗せることはない社風だと思います。会社としての制度やフォロー体制がしっかり整っているため、私が入社した20年前から、子育てをしながら活躍されている女性の先輩が多くいました。そうした姿を見てきたこともあり、私自身も安心して子どもを持つ決断をすることができたのです。
また私の場合、両親が近くに住んでいることや、インテージに在籍するパートナーが私の働き方に理解があることもあり、育休からの復帰後も思いきり仕事に打ち込むことができています。むしろ第一子の育休から復帰した当初は、子どもと離れる時間がリフレッシュになっていたほどです。現在は、私もパートナーも週2回ほど出社しています。互いに出社日をずらすことで、出社日は思いきり仕事をしたり自由に過ごしたりできていますし、家庭と仕事のバランスをうまく保てています。
とはいえ、育児と仕事の両立については常に考えています。現在私が担当している「SRI+」はインテージの主幹事業であり、非常に責任の大きいプロジェクトです。何度かプロジェクトに参画を打診されていましたが、育児もあり断っていました。参画を決めたタイミングは、前のプロジェクトが落ち着いてきたタイミングであったこと、そして子どもも成長して手がかからなくなってきたこともあり、「今だ!」と腹をくくってお引き受けしました。
今のところ、私のグループで出産や子育てをスタートしたメンバーはいませんが、今後そういったメンバーが現れた際には、恵まれた環境で子育てした自分のケースを元に考えるのではなく、その人の状況に合わせて柔軟に対応できるようにしたいと思っています。
節目ごとに見つめ直したキャリア
20代から30代中盤までは、約3年ごとに異動を繰り返し、どこでも、何でもやれるという自信がありました。30代後半からはゼネラリストとして突き進むこともできましたが、一つの領域に腰を据えてキャリアを築くことも大事と考えるようになり、現在のインサイトプラットフォーム本部で、システム開発に専念することを決めました。
また「自分のスキルは強みになっているか」という悩みができて、そんな時にグループリーダーというポジションを打診され、「人を育てる立場へシフトすることも、新たな価値になるのではないか」と考えるようになり、挑戦することを決めました。
そして40代中盤を迎えた今、メンバーや環境に恵まれている一方で、「このまま定年まで今の役割を続けていくのか」考えるようになりました。そんな中でグループリーダーを退いた後を想像するうちに、自分の居場所がないような漠然とした不安を感じるようになってきました。私自身は、現在のようなマネジメント業務に携わる前から、コーディングなどの手を動かす業務よりも、要件をヒアリングし理想の姿を描き、プロジェクトを推進する業務の方が自身の『適性に合っている』と考えていました。そのためメンバーが優秀でシステムが安定稼働している時は、手持ち無沙汰になることもあります。それにマネジメント中心の業務では、プレイヤーだった時のような自分ごととしての達成感や、誰かの役に立っているという実感が得にくくなります。また、現在のように内販のシステム開発を行っていると、関わる人や訪れる場所がある程度固定されているため、次第に緊張感も薄れてきます。
そんな時に、外販のシステム開発を行っていた入社当初は、顧客とたくさんコミュニケーションを取りながら仕事を進めることが楽しかったことを思い出し、営業など人と関わる業務へジョブチェンジすることも一つの選択肢かもしれないと考えるようになりました。
こうした考えに至ったきっかけは、「ドコモアカデミー」という新規事業などを考える研修でした。約3カ月にわたり、さまざまな人と関わる中で、そう思うようになったのです。
もしかするとこうしてもがく気持ちは、この先もずっと続くのかもしれません。でもそれさえもポジティブに捉えて、もがくこと自体を楽しめるようになるといいなと思っています。50代になるとキャリアも終盤と捉えて変化を恐れてしまう人もいるのかもしれませんが、私は最後まで自分がやりたいことに挑戦し続けていきたいと思っています。
今後の抱負とこれから入社する方へメッセージ
私は新卒で当社に入社したため、他の会社のことは正直わからないのですが、風通しが良い会社だと思います。私はいろいろな人に話しかけるタイプなのですが、社内には特定の派閥のようなものがなく、自分の思ったことをすぐに誰かに相談できる環境があります。そして誰に話しかけても話しやすいため、業務もスムーズに運びやすいと感じています。またグループリーダーによっては、私のように任せるスタイルの人もいれば、丁寧にフォローしてくれるスタイルの人もいますので、その人の個性に合わせて安心して働ける環境だと思います。
当社はシステム開発を行う会社ではありますが、私のようにプログラミングが得意ではない人もいますし、何か一つでも突出した強みがあって、それについてきちんと話すことができる人であれば、活躍できる会社だと思います。ぜひそんな仲間をお待ちしています。
この記事は取材当時(2025年7月1日)の内容です。